神話時代の夜
概要
機械文明と魔術の共存する世界。“神を殺す”ことを誓った賞金稼ぎは、人界に紛れ暮らす創世神の末裔たる少年に出会い、奇妙な共同生活を始める。さらに、ひねくれ者の妖族の少女も仲間となり、彼等の運命は複雑に絡み合い始める。2000.01.07-
人物
ナハト=ザーゲンツァイト(Nacht Sagenzeit)/外見16~17歳/男/身長164cm
・戦闘手段 : 格闘術、初等黒魔術、初等白魔術・その他特技等 : ギャンブル、手品、骨董品・美術品目利き
通称「チビ」もしくは「綿毛頭」。一見、軽くていい加減。普段はすねたり愚痴ったり、ダグと口喧嘩したりしているが、その奥には非常に虚無的な部分があり、あらゆる感情がどこか表面的に思われることがある。年齢不相応に老成した部分も多い。分類上は初等とはいえ、黒魔術と白魔術の両方を扱う異質な存在。また、ダグと知り合って4年程になるが、身体的変化(成長)は全く見られない。ちなみに、どれだけ呑んでも決して酔わず、薬物も種類によっては全く効かない。
「生きているものは、変わっていくことができる。逆に言えば、そうじゃないものは『生きてる』なんて言えないってことさ。例えばオレみたいにね」
※Nacht(独)…夜/Sagenzeit(独)…神話時代、神代の昔



ダグラス=トンプソン(Douglas Thompson)/30歳前後/男/身長182cm
・戦闘手段 : 高等白魔術、銃器一般・その他特技等 : 料理、機械類の扱い全般
通称「オッサン」もしくは「エセ牧師」。常に余裕を失わない不敵な男。察しが早く頭脳明晰で、臆する事を知らない豪胆さと、逸(はや)る事のない冷静さを併せ持つ。多少口は悪いが、感情をあらわにする事はなく、どこかひどく冷めている。幼い頃から神学系の教育機関で魔術を学び、若い頃には腕利きのエクソシストとして名を馳せた。しかしある事件(ステアを参照)がきっかけで一般市民の身分を捨て、闘いを求めてアウトローとなる。昔の名はダグラス=ウィンチェスター(Douglas Winchester)。
「…慣れてるんだよ。『ありがとう』なんて言われるより、『死んじまえバカヤロウ』って言われる方がな」
※Thompson…アメリカの銃技師。トンプソンM1短機関銃の生みの親として知られる。
※Winchester…銃器メーカー「ウィンチェスター・リピーティングアームズ(Winchester Repeating Arms)」、またその製品に冠せられる名。
※Winchester…銃器メーカー「ウィンチェスター・リピーティングアームズ(Winchester Repeating Arms)」、またその製品に冠せられる名。






リクセル=パールディム/外見15歳前後/女(妖族)/身長151cm
・戦闘手段 : 剣術、高等黒魔術・その他特技等 : 不明
無表情、無愛想、無遠慮。シニカルでやや退廃的な発言は、時に攻撃的なまでに辛辣。常に敬語で話すが、敬意は全く感じられない。何があろうと泣かないし笑わない、発展途上の情緒の持ち主。意外な所で世間知らずだったりする。妖族の中でも戦闘民族に近い血筋のため、容姿はまだほんの少女ながら、その身体能力は並の大人をはるかに上回る。また、寿命が長いため実年齢も見た目よりは高いらしいが、閉鎖的な環境で育ったためか、精神面ではそんな事はあまり判らない。




ルシア=ヴァルカージャ/外見10代後半~20代前半/女(種族不詳)/身長約165cm
神出鬼没の自称占い師。ナハトらに度々仕事を紹介してくれる情報屋である。性格は明るく能天気で、多少無責任。時折、刃物に惚れる性質がある。実は猫系のライカンスロープ(獣人)。

ニコル=ザウアー(Nicole Sauer)/24~25歳/男/身長約177cm
こちらも神出鬼没の、一見風来坊。銃器・火気類の売人でありスペシャリスト。ダグはお得意様。体格はとても細いが、喧嘩も充分人並以上にやるらしい。ヘビースモーカー。客に対してもわりと気安く振る舞うことが多い。ダグを「トンプソンの兄貴」、ナハトを「ボウズ」、リクセルを「姫さん」と呼ぶ。リクセルのファン。後にルシアの真の姿を知ることになる。意外と酒に弱い。※Sauer…スイスのSIG社及び当時傘下(現在は独立)ドイツのザウエル&ゾーン社が製造する自動拳銃。SIG SAUER P220、SIG SAUER P226、SIG SAUER P230など。「シグサワー」とも。

グリス=ギア/16歳(外見13歳前後)/男/身長148cm
ダグが「おやっさん」と慕う老エンジニアの、使いっ走り。拾われ子らしい。自信家で小生意気。口は悪いが腕はなかなか。ひねくれてはいるが、わかりやすい奴。ステア/シャドウステア/シュタイア=ベルグマン(Steyr Bergman)/女
ダグの学生時代の因縁の女性。ステアにはふたりの庇護者がいた。ひとりは物心つく前に捨てられたステアを拾い育てた男、イエーガー(“狩猟者”)。もうひとりはイエーガーの知人、ステアを養子に迎えた男、パウル=ベルグマン。イエーガーは現在のダグラスのように、公の身分を持たないジャック(賞金稼ぎ)であった。イエーガーは幼いステアに只ならぬ魔術の才気を感じ、魔術と闘いの術を教え込んで、彼女を自分の相棒に値するまでに育て上げた。その後ステアは神学院への進学を希望し、その法的権利を得るために、十代半ば頃、イエーガーの許を離れベルグマン家に養子として迎えられることになる。イエーガーに与えられたジャックとしての名は「シャドウステア」、パウルに与えられた法学院生としての名は「シュタイア=ベルグマン」という。“ステア”という呼称は、イエーガーの他はダグラスにしか教えていない特別なものである。
「勝算ゼロ。生還者ゼロ。その言葉が私を駆り立てるのさ」
ダグラスと共に神学院に在籍時、天使の名を冠する高位神族の一体が理性を失って戦闘行為を開始、俗に言う「堕天」が始まったとの知らせが入る。神学院の精鋭が為す術なく散っていく中、ステアはその討伐に向かう(エピソード「はじまりの刻」)が、ステアの魔力に目をつけたその神族は彼女を取り込み融合しようと総攻撃を仕掛けた。ステアは善戦したが神族に取り込まれ、戦闘の余波により街は神学院もろとも消滅した。その後ステアは神族に乗っ取られ堕天使と化したとも、その内部で未だ抵抗し神族の破壊行為を抑止しているとも噂されたが消息は知れない。
故郷とステアを奪われたダグラスは復讐とともに、望まぬ姿と成り果てたステアに引導を渡す決意をし、神属性存在に対抗しうる力を求めてジャックとなる。
※Steyr…銃器メーカー「シュタイヤーマンリヒャー(Steyr Mannlicher GmbH & KG)」、またその製品に冠せられる名。ステアーとも。

アーバント(Abend)
ナハトと対を成す創世神の末裔。ナハトと共に世界の“終末”を司る存在。時折ナハトに接触を試み、終末をもたらすべきだと持ちかけるが、ナハトはまだ早計だとして退け続けている。※Abend(独)…宵、夕方

設定
創世記  模式図へ
模式図へ
世界が形作られはじめた頃、そこにはいつしか、ひとつの巨大な意識体が存在していた。どこから迷い込んできたのか、あるいはどうやって生まれたのか、誰も知らない。原初の意識体、「原存在」と呼ばれる存在である。
それは莫大な情報量と、様々な思念を内包していた。それは変貌する天地を眼前にして更なる情報を獲得しながら、やがて激しく葛藤し始め、ついには分裂した。それぞれ方向性の異なる思念を宿した意識体は、各々の中にまた異なる思念を生じ、また分裂した。その次もまた、その次も。
そうしてそれらは限りなく分裂・分化を繰り返し、種々様々な生命となっていった。
まず原存在より、「監視者」と呼ばれる意識体が生まれた。それはその内に獲得した性質により、“変革”を司るものと“維持”を司るものに分かれ、“変革”を司るものは更に“開始”と“終止”とに分かれた。
“開始”を司る意識体は「モルゲン」、“終止”を司る意識体は「ナハト」、そして“維持”を司る意識体は「ターク」と呼ばれる。
ひとりめのナハトは、終末を司る者。世界を無に還す力を持つ者である。その役目を持ちながら、彼女は次第に、この世界を愛するようになってしまった。世界を終わらせたくないと強く望み、いつか訪れる終末を恐れ、それをもたらす自分の力を恐れた。その恐れのあまり彼女はついに、自らの存在を二者に分割し、それぞれを彼女自身とは異なる存在にした。
片方には、終末を司る使命の部分。他方には、世界を愛し終末を拒む思念が宿った。力を分割することで、その発現を食い止めようとしたのである。
彼女の分身のうち、使命を継いだ者には「アーバント」、終末を拒む者には彼女と同じ「ナハト」の名が与えられた。彼らは共に自らの生まれた理由を知り、彼女を「前身」ではなく「創造者」と認識する。
アーバントは使命を果たす日のため、終末をもたらす力を安定させるために、ナハトとの同化を望む。ナハトはそれを性急すぎると考え、拒み続けている。
※Morgen[独]…朝 / Tag[独]…昼 / Naght[独]…夜
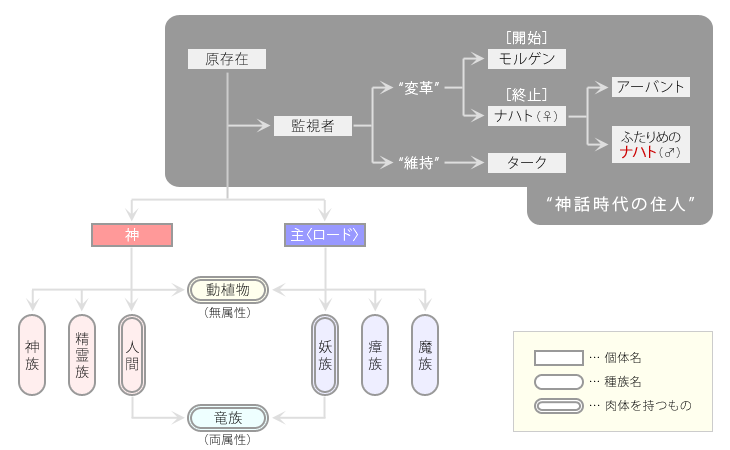
世界について
- モンスター 種族や行動理由は問わず、(一般の)人間にとって脅威たりえる力を持ち、見境なく暴れる(ように見える)ものを総じて「モンスター」と呼ぶ。
- スイーパー(駆逐者/掃除屋) モンスターを駆逐する者。また、その能力、それを生業とする者、それを中心あるいは専門に扱う賞金稼ぎ業、などを意味する。殆どは魔術士で、人間が圧倒的に多いが、妖族にもみられる。
- エクソシスト 瘴族の駆逐のみを専門に請け負う聖職者。金を取らない場合が多いなど、慈善的なイメージが強いため、スイーパーとは区別してこう呼ばれる。
- ジャック(賞金稼ぎ) 何でも屋(Jack of all trades)。定職に就かず、あるいは定職の裏で、私的な(しばしばイリーガルな)了解のもとに仕事で請け負って収入を得る者達の総称。仕事は通常「依頼」と呼ばれ、その依頼者は「依頼人(クライアント)」と呼ばれる。
割合から言えば屍鬼・妖族・瘴族が大多数だが、まれに魔族・竜族・精霊族・人間(もしくはその成れの果て)も含まれる。
スイーパーでないジャックも存在するが、その数は少ない。
ちなみに「Jack」には「金」の意もある。
魔術について
- 黒魔術と白魔術 神から分化した生命体は全て神の属性を帯び、主(ロード)から分化した生命体は全て魔の属性を帯びる。魔術の性能、外見に関わらず、神属性の力による魔術を白魔術、魔属性の力による魔術を黒魔術と呼ぶ。物質や肉体を破壊する際には両者の威力は殆ど変わらず、対象が「神」側か「魔」側かに偏っていればいるほど、その反対属性の魔術の効果は増大する。
- 精霊魔術 精霊を使役し、精霊の力を行使する魔術。当然、神と神族の力をいうわけだが、過去、人間でありながらこれを扱えた者がいたという伝説もある。魔術の性質としては、天候や地形を操るなど大規模なものと、生命体の運命や生死を操るなど潜在的で一見魔術とは判らないものとがある。
- 練気 魔法力を、魔術ではなく肉弾戦闘の技術に利用するものをこう呼ぶ。魔術に比べて習得が困難で、使い手も非常に少ない。魔術のように複雑なことは出来ないかわりに、呪文詠唱を必要とせず(その為に制御が困難となっている)、精神集中のみで行使できる。主に東方世界(イスタニー)で発展した。
- 魔術使い 魔術を顕現できる者というのは、そう稀な存在ではない。しかし、その力を完全に制御できる者は極めて少なく、加えてその力が実用になるほど強い者はさらに少ない。近年では、制御の利かない者の魔法力の暴走を抑える制御装置(指輪、ピアス等)も普及している。
- 魔法力 精神力の昇華した形で、他者(物質・精神問わず)に干渉する力をもったもの。魔術を直接構成するもの。常にエネルギーを放出し続ける不安定な存在。生成の仕方によって、見境なく外界に働きかける性質を持ったり(=魔法力の暴走)、生成者の意識に応じていくつかの単純な作用をする性質を持ったり(=練気)する場合もある。
- 呪文
| 区分 |
性能 |
白魔術 |
黒魔術 |
|---|---|---|---|
| 初等 |
催眠 |
いざなう甘き春の吐息を我が手に |
|
| 炎 |
怒れる熱き誓いの炎を我が手に |
華よ咲け、大気を喰らう朱(あか)き華 |
|
| 冷気 |
囁く白き冬の息吹を我が手に |
||
| 雷 |
空を裂く荒ぶる牙を我が手に |
雷(いかづち)よ踊れ、この手で牙を剥け |
|
| 中等 |
バリア |
輝く白き庇護の光を我が手に |
大気よ抗え、我に害なすものを阻め |
| 飛行・浮遊 |
天(あま)駆ける見えざる翼を我が手に |
大気よ凪げ、我を抱きてその意に従え |
|
| 治癒 |
さざめく青き慈悲の光を我が手に |
夜よ謡(うた)え、光に疲れし者を癒せ |
|
| 照明 |
導きの熱なき光を我が手に |
||
| 衝撃・振動 |
揺るがす風の怒りの声を我が手に |
||
| 高等 |
浄化/汚染 |
我と我が手に、祝福を、永遠(とわ)に気高き潔浄の光を |
|
| 死 |
命を狩る背徳の刃(やいば)を我が手に |
闇よ呼べ、迷い出ずる者を招き入れよ |
|
| 無(消滅) |
生ける屍、死せる魂、誇りなきものに無情の光を |
||
| 傀儡 |
まどろむ虹の招く言葉を我が手に |
||
| 幻惑 |
欺く霧の嗤(わら)う声を我が手に |
ナハト
彼はいつだって本気を出さない。無意識のうちに力をセーブする。彼と競える者が居なくなるのが怖いからだ。彼は絶対者の孤独から逃れるために人界に紛れている。同じ「絶対者」達では、彼の心は癒せない。自分と根本的に異なる者達でなければ、彼は面白くない。残酷な悠久の時を、失望に負けずに過ごすことができないのだ。もしも彼が失望に呑まれてしまう時は、母なるナハトの意思を放棄し、アーバントの使命にその力を委ねる時…即ち世界の終末である。
彼は数え切れないほど人間や妖族達と出会い、別れることを繰り返してきた。老いる事のない彼は人界では奇異だ。居心地のいい場所は、すぐに手放す時がやって来る。
彼がもしダグの許を去ると言えば、ダグは止めはしないだろう。ダグはすべてを知り、自分ではナハトを変える事は出来ないと悟るであろうからだ。また、神を敵に回す復讐劇に身を投じた彼は、人を名残惜しく思う気持ちに、それほど純粋になれないからだ。リクセルもまた、彼を止めはしないだろう。彼女の心はまだ息づき始めたばかりで、複雑な感情に戸惑うだけで精一杯だからだ。
ナハトは彼らのそうした心の動きを快く思い、そのような者達にまた出会える事を希望として去っていくのだろう。
三人三様の情緒
- ナハト 他人から見れば一番まともな少年。腹を立てたり不安がったり、時には中々の熱血漢であったりと感情表現は多彩だが、全ては計算の上の演技である。神族、魔族、竜族など、興味深い精神構造を持つ者ならどんな輩とでも生活を共にして永い時を過ごしてきた彼は、その膨大な精神容量を隠す技術をはじめ、記憶の制限(忘却)、感情、防衛などあらゆる精神機構をイミテイトする事が今では可能となっている。そしてそれらを、状況と自らの興味に応じて使い分け、使いこなしているというのが、彼の真の姿なのである。
- ダグラス ダグは怒らない。悲しまない。それは主に防衛によるもので、「神を殺す」という狂気じみた決意の所以たる過去の事件での、想像を絶する怒りと悲しみの反動。普段はそれは余裕や威圧感、冷静さとして表れプラスに働いているが、いざその決意を果たす時になれば暴発するかもしれない危ういもの。
- リクセル 結局のところ一番まともな精神を持つ(ことになる)のが、一番そうとは見えないリクセル。冷たい家庭で育まれた孤独で即物的、結果本位な性格は、怒りをはじめ寂しさや愛情、母性といった様々な情動を次第に獲得してゆく。
その他
- ダグラスの魔銃『ガルグイユ』 人間であるゆえに白魔術しか扱えないダグラスは、神と神に近き者を滅する為、黒魔術を帯びた魔銃を持つ。
- リクセルの魔剣 リクセルの携える剣は反りがあり片刃で、日本刀に似た形をしている。細身ながら切れ味と強度は驚異的。
『ガルグイユ』と呼ばれるその漆黒の魔銃は、犠牲者の魂を喰らい、喰らった魂の分だけその力を増していく忌まわしき銃。
ベースとなっている銃はデザート・イーグル。
※ガルグイユ(Gargoyle)…長い首を持ち、甲羅とヒレを持つ巨大な竜。体の中に大量の水を溜めることができ、さらにその水を一気に吐き出し洪水を引き起こすという。
意思を持つ金属生命体で形成されており、人の姿をとる事もできる。非常に高い魔法力を宿す。
リクセルはこの剣のおかげで、一部では「邪刀のリクセル」「鬼刃のリクセル」等の異名をとっている。
リクセル自身、剣のあまりの能力の高さをある意味疎ましく思いながらも、最早それ無しで身を守る事は難しいため、剣は片時も手放さない。
エピソード
各タイトルをクリックすると物語を表示します。もう一度クリックすると閉じます。瘴土使い
波のように押し寄せる、屍鬼の大群。視界の殆どが骸骨で埋め尽くされたかに思える、悪夢の光景だった。
ナハトはぎょっとしてダグの出方を窺うが、ダグは妙に落ち着いていた。独り言の様に、
「…古くからの集団墓地だな。手入れが行き届いてたから、さほど邪気も無いはずだ──気脈の変動なら、ここまで唐突なワケがない。するってえと、やっぱ…」
そこまで言うと、ダグは目を厳しくした。
「──瘴土使い、か!」
近接戦闘しか能がないに等しいナハトは、心細げにつぶやく。こいつらが街へ入ったら…。
「おい…どうすんだよ、オッサン」
「下がってろ。チビ」
ダグは半歩前に出ると、地平線の辺りを虚ろに見据えながら、恐ろしい気迫で精神を集中しはじめた。下ろしていた両手を、すうっ、と胸の前にかざす。そして、感情を殺した凍る様な声で、朗々と呪文をつむぎ出す。
『我と我が手に、祝福を。永遠(とわ)に気高き潔浄の光を!』
指揮でもするように、何かを抱き抱えるように、さっと両手を広げる。
途端。ダグのすぐ足元から、左右に大きく展開しながら、前方へ──白い、ほんの僅かに薄青い光が、地面に広がっていった。ダグを中心にして、およそ扇形に、しかしその半径は優に1kmはあろうかと思われた。光が山裾にまで達したのを見届けると、ダグは両手を伴って天を仰いだ。
───
水が一瞬で蒸発するような、乾いた音が辺り一帯に響き渡った。同時に、巨大な光の扇形が、天に向かって立ち昇るようにかき消えた。ややあって──まさに潮騒のような音がして、屍鬼の波がさざめき始めた。ナハトは、一瞬、目を疑った。
屍鬼たちが、力を失ってくずおれていく……これだけの大群が、一斉に!
ナハトは呆然とした。潮騒のようだった、屍鬼たちの崩れ落ちる音は、次第にがらがらと荒さを増していく。これほどの規模にわたる魔術は、そうそう見られるものではない──しかも、これだけ魔法力を消費したというのに、その背中には疲労の色すら見えない。
「……すげェ………。」
呆けたような笑みで呟きながら、ナハトの目は不可解な色を宿していた。驚愕、感嘆、畏敬、それらの奥に、何かとても懐かしいものを見たような穏やかな光が灯っていた。そして微かに、悲哀、あるいは寂しさに似た色彩すら漂っていた。
「墓荒らしは嫌いなんだよ」
毒づくダグは、それには気付かない。久々に見せた怒りに、彼自身やや困惑もしていた。
ナハトはぎょっとしてダグの出方を窺うが、ダグは妙に落ち着いていた。独り言の様に、
「…古くからの集団墓地だな。手入れが行き届いてたから、さほど邪気も無いはずだ──気脈の変動なら、ここまで唐突なワケがない。するってえと、やっぱ…」
そこまで言うと、ダグは目を厳しくした。
「──瘴土使い、か!」
近接戦闘しか能がないに等しいナハトは、心細げにつぶやく。こいつらが街へ入ったら…。
「おい…どうすんだよ、オッサン」
「下がってろ。チビ」
ダグは半歩前に出ると、地平線の辺りを虚ろに見据えながら、恐ろしい気迫で精神を集中しはじめた。下ろしていた両手を、すうっ、と胸の前にかざす。そして、感情を殺した凍る様な声で、朗々と呪文をつむぎ出す。
『我と我が手に、祝福を。永遠(とわ)に気高き潔浄の光を!』
指揮でもするように、何かを抱き抱えるように、さっと両手を広げる。
途端。ダグのすぐ足元から、左右に大きく展開しながら、前方へ──白い、ほんの僅かに薄青い光が、地面に広がっていった。ダグを中心にして、およそ扇形に、しかしその半径は優に1kmはあろうかと思われた。光が山裾にまで達したのを見届けると、ダグは両手を伴って天を仰いだ。
───
水が一瞬で蒸発するような、乾いた音が辺り一帯に響き渡った。同時に、巨大な光の扇形が、天に向かって立ち昇るようにかき消えた。ややあって──まさに潮騒のような音がして、屍鬼の波がさざめき始めた。ナハトは、一瞬、目を疑った。
屍鬼たちが、力を失ってくずおれていく……これだけの大群が、一斉に!
ナハトは呆然とした。潮騒のようだった、屍鬼たちの崩れ落ちる音は、次第にがらがらと荒さを増していく。これほどの規模にわたる魔術は、そうそう見られるものではない──しかも、これだけ魔法力を消費したというのに、その背中には疲労の色すら見えない。
「……すげェ………。」
呆けたような笑みで呟きながら、ナハトの目は不可解な色を宿していた。驚愕、感嘆、畏敬、それらの奥に、何かとても懐かしいものを見たような穏やかな光が灯っていた。そして微かに、悲哀、あるいは寂しさに似た色彩すら漂っていた。
「墓荒らしは嫌いなんだよ」
毒づくダグは、それには気付かない。久々に見せた怒りに、彼自身やや困惑もしていた。
[ 閉じる ]
はじまりの刻
「どうしても、行くのか?」
何気ない調子で青年は尋ねた。逆光に翳って、相手の表情は分からない。しかし返す声は、薄笑いするような響きをもっていた。
「…分かって訊いているだろう、お前」
そう言われた青年は、図星というように少し頭を掻いた。
「お前はそういう性分だものな」
そう続けると、声の主はまた夕陽の方へ向き直った。ふたりの立つ小さな山からは、彼らの町が一望できる。教会と学校を中心に雑然と家々がひしめき合い、所々にはビル群も顔を見せている。家並みがまばらになってゆく町のはずれは、なだらかな丘陵地帯となっている。その丘のひとつへ、陽は沈んでゆこうとしていた。初冬の雲はやたらくっきりとした輪郭で、落日に彩りを添えていた。
不意に人影は青年を振り返った。
合わせたように吹き上げる風が、彼らの髪をばたばたと弄んだ。
「──ダグラス。もう二度と、会うことはないだろう。もしもあったら、その時は…」
「…分かってる」
青年の声は落ち着いていたが、どこか必死であるようにも思われた。
返す声は風にさらわれ、青年の耳には届かなかった。
何気ない調子で青年は尋ねた。逆光に翳って、相手の表情は分からない。しかし返す声は、薄笑いするような響きをもっていた。
「…分かって訊いているだろう、お前」
そう言われた青年は、図星というように少し頭を掻いた。
「お前はそういう性分だものな」
そう続けると、声の主はまた夕陽の方へ向き直った。ふたりの立つ小さな山からは、彼らの町が一望できる。教会と学校を中心に雑然と家々がひしめき合い、所々にはビル群も顔を見せている。家並みがまばらになってゆく町のはずれは、なだらかな丘陵地帯となっている。その丘のひとつへ、陽は沈んでゆこうとしていた。初冬の雲はやたらくっきりとした輪郭で、落日に彩りを添えていた。
不意に人影は青年を振り返った。
合わせたように吹き上げる風が、彼らの髪をばたばたと弄んだ。
「──ダグラス。もう二度と、会うことはないだろう。もしもあったら、その時は…」
「…分かってる」
青年の声は落ち着いていたが、どこか必死であるようにも思われた。
返す声は風にさらわれ、青年の耳には届かなかった。
[ 閉じる ]
風変わりな仲間
「よう。奇遇だな」
「何が奇遇ですか。探していたんでしょう?人数合わせに」
刺々しい言葉とは裏腹に、彼女の目に批判や不機嫌の色は無い。もともと、こういう物言いなのだ。
「人数合わせとはご挨拶だな。今回は本当に、お前の力が必要なんだよ」
「何故です?」
「式神使いを、敵に回す事になるんでな。それも一人や二人じゃない、一私兵団だ」
リクセルはこんどは言い返さず、代わりにきろりと視線を投げた。冷静に、しかし明らかに何かを示唆するその光は、ダグの──顔ではなく、懐に。即ち、あの漆黒のデザート・イーグルの在処に向けられていた。
神に近き者を滅する力…貴方にも、無い事はないんでしょう? そう言っていた。
目で物を言うようになったリクセルを内心微笑ましく思いつつ、ダグは柔らかな視線で応えた。
まだ少しばかり早すぎるんだよ、と。
「やってくれるよな?」
「…わかりました」
「何が奇遇ですか。探していたんでしょう?人数合わせに」
刺々しい言葉とは裏腹に、彼女の目に批判や不機嫌の色は無い。もともと、こういう物言いなのだ。
「人数合わせとはご挨拶だな。今回は本当に、お前の力が必要なんだよ」
「何故です?」
「式神使いを、敵に回す事になるんでな。それも一人や二人じゃない、一私兵団だ」
リクセルはこんどは言い返さず、代わりにきろりと視線を投げた。冷静に、しかし明らかに何かを示唆するその光は、ダグの──顔ではなく、懐に。即ち、あの漆黒のデザート・イーグルの在処に向けられていた。
神に近き者を滅する力…貴方にも、無い事はないんでしょう? そう言っていた。
目で物を言うようになったリクセルを内心微笑ましく思いつつ、ダグは柔らかな視線で応えた。
まだ少しばかり早すぎるんだよ、と。
「やってくれるよな?」
「…わかりました」
[ 閉じる ]
真昼の異邦人
その日は朝から、夕立のような豪雨であった。
ダグは暇そうにタバコをふかし、ナハトはもっと暇そうにソファでレンチを弄んでいた。投げやりにぱったりと仰向けになると、
「腹減ったーーー」
「大声出すと、よけい減るぞ」
「………」
ここ最近、仕事がないのである。
賞金稼ぎ(ジャック)は運任せの稼業だ。いくら腕が良かろうが、無い時には一件の依頼も無い。だから別に定職を持っている者もいるのだが、真っ当な職に就くにはそれなりの身分が必要だし、それは大仕事の際には思わぬ邪魔になる事がある。だからダグは表の顔は持たない。従って、運の悪い時には人知れず空腹に耐えるしかない。
唐突に、呼び鈴が響き渡った。ダグが扉を開けると、そこには濡れねずみの少女が立っていた。ダグが口を開くより先に、彼女はにっこりと笑って言った。
「今日は。良い天気ですね」
「……は?」
ダグが呆気に取られている隙に、少女はスタスタとアジトに上がり込んで行った。ナハトが跳ねるように起き上がって珍妙な侵入者を凝視する。
「お邪魔します」
ダグにしたのと同じ笑顔をナハトにも向け、少女は明るく会釈すると、そのまま迷いもせずシャワールームに向っていった。間もなく水音が流れ出す。
二人の住人は呆然と顔を見合わせる。ナハトが脱力した手でシャワールームの方を指差し、
「……あの……なに?あれ…」
「…理解不能の存在だ。ま、大して害は無さそうだが」
ダグが頭を掻きつつ玄関先から戻って来る。
「メシの種(依頼人)かと思ったんだがなあ。どう思う、チビ」
「どうって…」
傍若無人というより、夢遊病者か幻覚を見ている人間のような行動だ。と、ぼんやり考える。
それより何故、彼女はシャワールームの位置や扱い方が分かるのか。更に何故ダグはそれに大して動じていないのか…。ナハトとしては、後者の方が不思議だった。
ほんの数分後、どこから出したのかバスローブを羽織り、三人分のコーヒーまで淹れて、少女は粗末な応接室に鎮座していた。一応は平静なダグ、まだ狐につままれたようなナハトを前に、少女はにこにこと微笑んでいる。
歳は18かそこらだろうか。顔立ちや背格好はそんな所だが、表情や仕種は年齢の問題ではなかった。ダグが扉を開けた時からずっとそうなのだが、底抜けに晴れやかな、というかのどかな笑顔。春のいい日和に猫が日向ぼっこでもしているようだ。
少女の行動には微塵の迷いも感じられない。道徳的に有って然るべき遠慮や躊躇いの欠如はともかく、どうやって知ったのか、他人の住居をさも慣れた様子で歩き回る。監視や盗聴の類にはそれなりに気を遣っていた筈なのに…勿論一般人の「それなり」とは程度が違う。ジャックとして営業妨害や危害を受けない為の、自衛である。
少女はコーヒーカップを口へ運ぶ。ぱらりと揺れる濡れ髪は丁度上質のコーヒーのような焦茶色をして、ゆったりとしたウェーブを描いている。どうやら黄色人種だがそれにしては白く、中々の器量良しと言っていい。
「さてと。賞金稼ぎの、ダグラス=トンプソンさん、ですよね?」
コーヒーカップをことりと置き、無邪気な調子で少女は尋ねる。久々にフルネームを呼ばれたダグはほんの僅か表情を鋭くしたが、驚いたという程ではないようだった。
「“賞金稼ぎ(ジャック)の”ってことは…あんたは、依頼人(クライアント)さんなのかな?」
「はい。ナツメ・クギョウと申します」
「クギョウ?」
今度はナハトが表情を変えた。クギョウと言えば東方(イスタニー)における巫術の大家である。その御令嬢が単身こんな所に?しかし本当にクギョウ家の巫術使いだとすれば、他人の目を借りてその住居を窺い知るくらいは朝飯前であろう。伝統を守り秩序を尊ぶ筈の東方で、何らかの動きが起きているのか?ナハトの頭の中では、ダグが予想だにしないであろう情報が整理されていった。
ダグは暇そうにタバコをふかし、ナハトはもっと暇そうにソファでレンチを弄んでいた。投げやりにぱったりと仰向けになると、
「腹減ったーーー」
「大声出すと、よけい減るぞ」
「………」
ここ最近、仕事がないのである。
賞金稼ぎ(ジャック)は運任せの稼業だ。いくら腕が良かろうが、無い時には一件の依頼も無い。だから別に定職を持っている者もいるのだが、真っ当な職に就くにはそれなりの身分が必要だし、それは大仕事の際には思わぬ邪魔になる事がある。だからダグは表の顔は持たない。従って、運の悪い時には人知れず空腹に耐えるしかない。
唐突に、呼び鈴が響き渡った。ダグが扉を開けると、そこには濡れねずみの少女が立っていた。ダグが口を開くより先に、彼女はにっこりと笑って言った。
「今日は。良い天気ですね」
「……は?」
ダグが呆気に取られている隙に、少女はスタスタとアジトに上がり込んで行った。ナハトが跳ねるように起き上がって珍妙な侵入者を凝視する。
「お邪魔します」
ダグにしたのと同じ笑顔をナハトにも向け、少女は明るく会釈すると、そのまま迷いもせずシャワールームに向っていった。間もなく水音が流れ出す。
二人の住人は呆然と顔を見合わせる。ナハトが脱力した手でシャワールームの方を指差し、
「……あの……なに?あれ…」
「…理解不能の存在だ。ま、大して害は無さそうだが」
ダグが頭を掻きつつ玄関先から戻って来る。
「メシの種(依頼人)かと思ったんだがなあ。どう思う、チビ」
「どうって…」
傍若無人というより、夢遊病者か幻覚を見ている人間のような行動だ。と、ぼんやり考える。
それより何故、彼女はシャワールームの位置や扱い方が分かるのか。更に何故ダグはそれに大して動じていないのか…。ナハトとしては、後者の方が不思議だった。
ほんの数分後、どこから出したのかバスローブを羽織り、三人分のコーヒーまで淹れて、少女は粗末な応接室に鎮座していた。一応は平静なダグ、まだ狐につままれたようなナハトを前に、少女はにこにこと微笑んでいる。
歳は18かそこらだろうか。顔立ちや背格好はそんな所だが、表情や仕種は年齢の問題ではなかった。ダグが扉を開けた時からずっとそうなのだが、底抜けに晴れやかな、というかのどかな笑顔。春のいい日和に猫が日向ぼっこでもしているようだ。
少女の行動には微塵の迷いも感じられない。道徳的に有って然るべき遠慮や躊躇いの欠如はともかく、どうやって知ったのか、他人の住居をさも慣れた様子で歩き回る。監視や盗聴の類にはそれなりに気を遣っていた筈なのに…勿論一般人の「それなり」とは程度が違う。ジャックとして営業妨害や危害を受けない為の、自衛である。
少女はコーヒーカップを口へ運ぶ。ぱらりと揺れる濡れ髪は丁度上質のコーヒーのような焦茶色をして、ゆったりとしたウェーブを描いている。どうやら黄色人種だがそれにしては白く、中々の器量良しと言っていい。
「さてと。賞金稼ぎの、ダグラス=トンプソンさん、ですよね?」
コーヒーカップをことりと置き、無邪気な調子で少女は尋ねる。久々にフルネームを呼ばれたダグはほんの僅か表情を鋭くしたが、驚いたという程ではないようだった。
「“賞金稼ぎ(ジャック)の”ってことは…あんたは、依頼人(クライアント)さんなのかな?」
「はい。ナツメ・クギョウと申します」
「クギョウ?」
今度はナハトが表情を変えた。クギョウと言えば東方(イスタニー)における巫術の大家である。その御令嬢が単身こんな所に?しかし本当にクギョウ家の巫術使いだとすれば、他人の目を借りてその住居を窺い知るくらいは朝飯前であろう。伝統を守り秩序を尊ぶ筈の東方で、何らかの動きが起きているのか?ナハトの頭の中では、ダグが予想だにしないであろう情報が整理されていった。
[ 閉じる ]
もしもあったら、その時は
壮絶な戦いの末、ダグは遂にステアを打ち倒した。魔銃ガルグイユが彼女の力を使い果たさせ、エネルギー翼と戦闘外殻を剥ぎ取り、幾年月を経て「人間」へと戻った彼女は地上に落ちていった。
落下地点へ辿り着いたダグは、命を繋ぐ為に最低限の治癒魔術を施してはいたが満身創痍であった。半ばぼやけた視界の中、彼は瓦礫に倒れかかるステアの姿を捉えた。
足を引き摺り近付くダグにステアは顔を上げ、穏やかに微笑んだ。
それは懐かしい面影、出会った頃の若かりしステアそのものだった。先程までの死闘も、あの日に見た異形も、全て悪い夢だったのではないかと思うほどに、静謐な時が二人の間を満たしていた。
「…手を貸してくれないか?立ち上がれないんだ…」
朦朧とする意識の中、ダグは言われるままに手を伸べる。
二人の指先が僅かに触れるかという瞬間、ダグははっと正気に返った。極神属性存在に魂の底まで汚染され、魔属性攻撃による相殺でその力を引き剥がされたステアの物理身体は、外見上その形を保っていても魔力理論上は薄氷の如く脆いはずだ。そこに魔力を備えた生物との接触が加われば…だが、もう遅かった。
ステアの肉体はダグに触れた指先から霧と消えていく。咄嗟に彼女を繋ぎとめようとするダグだが、ステアに触れるその手は消滅を早めるだけ。どうしようもない焦燥にダグはステアの顔を見上げる。彼女の微笑はあまりにも優しく、そしてどこか、謝るような目をしていた。
「───」
一瞬の躊躇い、そして、ダグは彼女を抱き締めた。最早抗えない結末ならば、このままただ見守っているよりも、たった一つの願いを叶えたかった。
全身でダグに触れたステアの身体は瞬く間に霧散し、ダグの腕は支えを失って空を切った。
“有難う”
そんな声が、聞こえた気がした。
落下地点へ辿り着いたダグは、命を繋ぐ為に最低限の治癒魔術を施してはいたが満身創痍であった。半ばぼやけた視界の中、彼は瓦礫に倒れかかるステアの姿を捉えた。
足を引き摺り近付くダグにステアは顔を上げ、穏やかに微笑んだ。
それは懐かしい面影、出会った頃の若かりしステアそのものだった。先程までの死闘も、あの日に見た異形も、全て悪い夢だったのではないかと思うほどに、静謐な時が二人の間を満たしていた。
「…手を貸してくれないか?立ち上がれないんだ…」
朦朧とする意識の中、ダグは言われるままに手を伸べる。
二人の指先が僅かに触れるかという瞬間、ダグははっと正気に返った。極神属性存在に魂の底まで汚染され、魔属性攻撃による相殺でその力を引き剥がされたステアの物理身体は、外見上その形を保っていても魔力理論上は薄氷の如く脆いはずだ。そこに魔力を備えた生物との接触が加われば…だが、もう遅かった。
ステアの肉体はダグに触れた指先から霧と消えていく。咄嗟に彼女を繋ぎとめようとするダグだが、ステアに触れるその手は消滅を早めるだけ。どうしようもない焦燥にダグはステアの顔を見上げる。彼女の微笑はあまりにも優しく、そしてどこか、謝るような目をしていた。
「───」
一瞬の躊躇い、そして、ダグは彼女を抱き締めた。最早抗えない結末ならば、このままただ見守っているよりも、たった一つの願いを叶えたかった。
全身でダグに触れたステアの身体は瞬く間に霧散し、ダグの腕は支えを失って空を切った。
“有難う”
そんな声が、聞こえた気がした。
[ 閉じる ]
エピローグ
ステアとの対決を終えたダグは別人のように無気力になり、何をするでもなくアジトに篭っていた。
ナハトはそんなダグの姿に観察対象として見切りをつけたのか、既に彼の元を離れていた。来訪者といえば、時折身の周りの世話をしに来るリクセルのみ。
その日もダグはベッドに腰掛け、虚空を眺めるばかりだった。
「俺の命はあいつを葬る為だけにあった。その目的が果された今、生きる意味など…」
無造作に転がっていたガルグイユを手に取り、銃口をこめかみに押し当てるダグ。
がちり、と鈍い音。
溜め込んだ力の全てを放出し魔力を失ったガルグイユは、通常の弾丸も発射できないガラクタと化していた。
「…自殺…?自殺だって?いつ誰に奪られるか判らない命を、わざわざ自分で?
……
くだらねえ…」
ガルグイユを放り出したダグは、いつしか笑い出していた。乾いた笑いは次第に大きくなり、ダグはベッドから落ちんばかりに笑い転げた。ステアが去ったあの日から、いや物心ついて此の方、これほど笑った事はなかった。そして丁度訪ねてきたリクセルが、この男も遂に狂ったかと隣室で聞き耳を立て始めた頃、はたと笑い止んだ。
「生きる目的がなんだ。今こそ、俺は自由だ」
ドアが乱暴に蹴り開けられ、様子を伺っていたリクセルは仔ウサギの様に跳び上がった。
「オイ。探しに行くぞ、あの綿毛頭を」
得意のポーカーフェイスでも動揺を隠しきれないリクセルは、ダグの顔を見て変化に気付く。
(笑ってる…)
それは初めて見る表情だった。ステアを倒すと決意した時から感情を凍らせたダグの笑い顔は、威圧か嘲笑の冷たい笑みでしかなかった。それが今は、笑っている。手段としてではなく己自身の感情から、真に笑っているのだ。
「…何が、あったんですか」
「あ?」
「とぼけないで下さい。初めて見ましたよ、貴方の『笑った』顔を」
「……ふん。言うね、お前も」
そう笑いながらダグは手早く装備を整え、いつものアタッシュケースに銃を詰め込み、コートを羽織るとサングラスをぐいと押し込んだ。
「さあて、どこに行ったあのチビ。あいつが居なけりゃ面白くない、そうだろう」
リクセルは信じられないものを見る心地だった。彼が立ち直る事を願って世話をしに来ていたが、こうも突然に事態が動くとは。ダグラスとはこんな男だったか。自分の知る彼とは少し違う、しかしきっと、これでいい。リクセルは表情を明るくし、ダグの背中をついていった。
「……はい!」
街へ繰り出したダグとリクセルを、ナハトは遠くから見ていた。彼らと共に過ごしたナハト少年の肉体構成を解除し、不可視の意識存在へと戻ったナハトは面白げに見ていた。
「目的を果たし、目的を失う…人間にはよくある事だ。あれもそのまま腐ってしまうかと思ったが…
やはり、人間は面白い!
さて、このまま隠れんぼを楽しもうか、元通りにひょっこり戻ってやるか…全く別の存在として近付くのも面白そうだ。ひとまず、もう少しあいつらと遊ぶとしよう」
ナハトはそんなダグの姿に観察対象として見切りをつけたのか、既に彼の元を離れていた。来訪者といえば、時折身の周りの世話をしに来るリクセルのみ。
その日もダグはベッドに腰掛け、虚空を眺めるばかりだった。
「俺の命はあいつを葬る為だけにあった。その目的が果された今、生きる意味など…」
無造作に転がっていたガルグイユを手に取り、銃口をこめかみに押し当てるダグ。
がちり、と鈍い音。
溜め込んだ力の全てを放出し魔力を失ったガルグイユは、通常の弾丸も発射できないガラクタと化していた。
「…自殺…?自殺だって?いつ誰に奪られるか判らない命を、わざわざ自分で?
……
くだらねえ…」
ガルグイユを放り出したダグは、いつしか笑い出していた。乾いた笑いは次第に大きくなり、ダグはベッドから落ちんばかりに笑い転げた。ステアが去ったあの日から、いや物心ついて此の方、これほど笑った事はなかった。そして丁度訪ねてきたリクセルが、この男も遂に狂ったかと隣室で聞き耳を立て始めた頃、はたと笑い止んだ。
「生きる目的がなんだ。今こそ、俺は自由だ」
ドアが乱暴に蹴り開けられ、様子を伺っていたリクセルは仔ウサギの様に跳び上がった。
「オイ。探しに行くぞ、あの綿毛頭を」
得意のポーカーフェイスでも動揺を隠しきれないリクセルは、ダグの顔を見て変化に気付く。
(笑ってる…)
それは初めて見る表情だった。ステアを倒すと決意した時から感情を凍らせたダグの笑い顔は、威圧か嘲笑の冷たい笑みでしかなかった。それが今は、笑っている。手段としてではなく己自身の感情から、真に笑っているのだ。
「…何が、あったんですか」
「あ?」
「とぼけないで下さい。初めて見ましたよ、貴方の『笑った』顔を」
「……ふん。言うね、お前も」
そう笑いながらダグは手早く装備を整え、いつものアタッシュケースに銃を詰め込み、コートを羽織るとサングラスをぐいと押し込んだ。
「さあて、どこに行ったあのチビ。あいつが居なけりゃ面白くない、そうだろう」
リクセルは信じられないものを見る心地だった。彼が立ち直る事を願って世話をしに来ていたが、こうも突然に事態が動くとは。ダグラスとはこんな男だったか。自分の知る彼とは少し違う、しかしきっと、これでいい。リクセルは表情を明るくし、ダグの背中をついていった。
「……はい!」
街へ繰り出したダグとリクセルを、ナハトは遠くから見ていた。彼らと共に過ごしたナハト少年の肉体構成を解除し、不可視の意識存在へと戻ったナハトは面白げに見ていた。
「目的を果たし、目的を失う…人間にはよくある事だ。あれもそのまま腐ってしまうかと思ったが…
やはり、人間は面白い!
さて、このまま隠れんぼを楽しもうか、元通りにひょっこり戻ってやるか…全く別の存在として近付くのも面白そうだ。ひとまず、もう少しあいつらと遊ぶとしよう」
[ 閉じる ]
© 2007 よこ